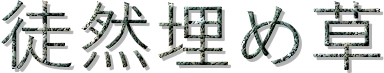日本語
| 漢字を使い過ぎる |
|---|
| 2024年2月1日 |
日本語学習者とSNSでやり取りすると、日本人でさえ書けないような難しい漢字を当たり前のように使って書いてくるので驚く。よく勉強しているな、と感心しているわけではない。まじめに日本語習得を目指している学習者が、不自然な日本語を覚えてしまう現実に腹が立つのだ。 例えば、「おいしい」を「美味しい」と書く。「うまい」を「美味い」「上手い」と書いたりする。「ためらう」を「躊躇う」と書く。「色々」「様々」「又」など、学校教育とずれのある表記を当然のように多用する。これは日本人の若い世代についても例外でなく、決して日本語力が向上しているわけでもないのに、常用漢字表にもない難しい漢字や、古くさい当て字を使う。いや、日本語力が落ちているからこそ、パソコン、スマホの漢字変換を吟味することもなく、ただ流している結果かもしれない。 日本語学習者はこれに加えて、日本のアニメやマンガ、ゲームに親しんでいる人が多い。アニメやゲームを楽しみたいということが、日本語を勉強したいという動機になっていることも少なくない。そのアニメやゲームが恐ろしく標準から離れた言葉遣いやあり得ない漢字を使ったりもする。 一方、まじめな学習者は辞書をよく引くだろうが、幅広い用途に対応する国語辞典は現代では使用の推奨されない、戦前の小説に出てくるような漢字も見出しに並べていて区別がつかない。学習者は、これらを標準であるかのように誤認して、自らの語彙に取り入れる。 こうした構造は日本語文化に根本的な影響を与えているが、社会的な関心は決して高くないように見える。 |
| |
| 乱れか拡大か |
|---|
| 2024年12月14日 |
| ひと昔前までは、日本語の乱れに半ばあきれながら「ばかなヤツが多くて困ったものだ」ぐらいに思っていた。しかし、すでに世の中は大変わりしていて、何が誤用で何が乱れで、何が慣用で何が許容で何が正用か、個人的な感覚を主張したところですぐに現実の大波に流されて、よりどころは消えてしまう。 何年か前、しばらくぶりで顔を合わせた若い世代に「〇〇さんとは10月ぶりですね」と言われて面食らったが、調べてみるとその10年以上前からすでにこうした使用例を見つけることができた。「卒業式ぶりに会った先生」など、私に言わせれば日本語に無知でその自覚もない誰かが自分勝手に使い、同種の人たちが追随して広がったのだろう。どのレベルの人も遠慮なく発信できるネットの世界は、その影響拡散のスピード、威力も激しく、「悪貨は良貨を駆逐する」どころではない。やがて「2000年ぶりに再会した」などというSFのような会話が当たり前になるのだろうか。 最近では「うれしみを感じるよね」「その話は納得みがある」「分かりみしかないね」などという「〜み」の使い方に危機感さえ覚える。これを用語法の拡大、拡張とする「理解」ある見方もあるだろうが、何でもそう言ってしまえば「法則み!」も「秩序み!」も存在しなくなる。 |
| |
| 「いい」と「よい」は違う |
|---|
| 2024年12月14日 |
| タイトルを見て「ん?」と思う人がいるだろう。「同じじゃないか」と。 もちろん同じ場合もあるが、細かく見ていくと相当に違う。ただ、日常、あまりそれを意識しない。よく考えると不思議な日本語ー。 何か望ましい話を聞いたときに、どう相づちを打つだろうか。「それはいい」か「それはよい」か。 何かを否定したり嫌がったり、必要ないと指示したりするときはどうだろう。「それはいい」か「それはよい」か。 普通の会話であれば、前者が多いのではないか。会話で「それはよい」と聞くと、時代劇の武士のせりふか、せいぜい戦前までの偉そうな言葉遣いという印象を受けてしまう。 「いい」は「よい」よりくだけた、口語的な形だ。日常よく使うのは「いい」の方だろう。だが標準的には、「よくない」とは言っても「いくない」とは言わない(言う地方はある)。「いい」は辞書形(終止形、連体形)としてしか使われず、否定形がない。なぜこんな中途半端な落ち着かない文法が生き続けているのだろう。 私が考えていなかっただけで、何をいまさら、と言われそうだが、深く探求するには熱意が不足している。ここは、思いつく表現を羅列するだけでとりあえず「いし」としよう。いや、そんな言葉はなかった。「よし」としよう。 〇よくない(×いくない) 〇よかった(×いかった) 〇よく似ている(×いく似ている) 〇それでよい!(〇それでいい!) 〇それでよし!(×それでいし!) 〇ちょうどよさそう(×ちょうどいさそう) 〇いい迷惑だ(×よい迷惑だ) 〇いい年をしてみっともない(×よい年をしてみっともない) 〇いい大人のやることじゃない(×よい大人のやることじゃない) 〇遊んでいていいよ(△遊んでいてよいよ) 〇これ頼んでいいかな?(△これ頼んでよいかな?) |
| |