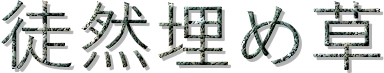目次
経営者の不作為>
企業に徳はないが>
人材の非活用>
在職死亡と特進>
悪夢−なぜ今ごろ>
メルケル首相>
過剰敬語>
| 悪夢ーなぜ今ごろ |
| ○年○月○日 |
ここ半年ぐらいだろうか、約束の時間に遅れる夢を繰り返し見る。
それは、どうしても出なければならない会議であったり、外せない会合であったり、
用件はさまざまだが、すべて間に合わないことが許されない日程である点が共通している。
もう一つの特徴は、会合などにぎりぎり間に合いそうで会場に必死で急ぐ、という直接的な内容ではなく、
その前の時点ですでに交通機関に遅れて絶体絶命になり、取り返しがつかないという展開になることだ。
例えば、空港までの所要時間を甘く見て余裕がなくなり、まず飛行機のテイクオフ(チェックイン)に遅れてしまう。
その便に乗れないことで、約束の時刻に約束の場所に着くことが絶対にできなくなってしまう、というパターン。
あるいは、所要時間を考えて今度は大丈夫と余裕をもって長距離バスのターミナルに着くと、
何とバスは1日に3便しかなく、もうその日は終わっている。
翌日の始発では、間に合わない、というもの。
あるいは、ぎりぎり間に合った、と安堵して列車の駅に着いてみると、
切符売り場の窓口が一つしかなく、長い列ができていて、
発車時刻が迫る中、じりじりしながら並ぶが切符を売ってもらえない。
結局、乗るべき列車は出てしまい、結果として約束にも遅れる。
あるいは、バス停で待っていてもバスが来ず、
とっくに時刻が過ぎてから実は運行ルートが違っていたのだと気付く。
バスは別ルートですでに行ってしまい後の祭りだ。
年齢的には比較的若い感じがする。
出張からの帰社や、帰省した自宅から単身赴任先への移動という感じの夢もある。
場所は、東京−自宅間らしいものもあれば、
どこか分からない、人のいない地方のバス停だったり、小さな鉄道の駅だったりもする。
かつて、こういう失敗をしたことはなく(しそうなことは確かにあったが)、
出てくる場面(駅や空港など)も見た覚えがない。
ああ、もうどうしようもない、打つ手はない−という追い詰められた、逃げ道のない心境にはなるのだが、
眠りながらずるさが出るのか、なぜか、じわじわと夢だと分かってきて、窮地から救われる。
すでに、時間については極めて緩い生活をしているので、どうして今ごろ、こんな夢を見るのか分からない。
だから面白いのだが。
⇒PAGE TOP
| 人材の非活用 |
| ○年○月○日 |
つくづく、もったいないと思う。
経営が大変な会社でも、窓際でほとんど暇を持て余している管理職を多数抱えている。
決して彼らに能力がないというわけではない。
大きな企業なら、採用の時点で相対的に競争力を持ち、本当に必要な中小企業に渡さずに
そこそこの人材を囲い込んでいる。
ところが、人事が回らなくなって、彼らが余ってしまうのだ。
自らは年功序列の恩恵にあずかっているにもかかわらず、
年功序列は「悪」だと思っている経営陣が多いから、幹部の若返りを無理に図ったりする。
幹部の選別は、公正と言えない場合が多いのに。
出世競争で、ライバルよりちょっと前に出ると、
わずかの実力差しかない人間は、たたいて水から上がれないようにするのがいい。
自分と立場が入れ替わる可能性があるからだ。
だから、力量に開きのある「自分を凌駕する心配のない」人間を、安全な幹部候補にする。
大学教授が自らを超えない准教授を選んで権力を維持するように、
イエスマンで周辺を固めておけば安心なのだ。
十分に力を発揮できる人を干しておいて、人材の持ち腐れというか、飼い殺しというか。
それができるうちは余裕のある企業とも言えるのだが、こんなことをやっていたら、このご時世、
早晩だめな会社になっていく。
有能な人間の活用をしないという直接的な損失に加えて、
こうした組織を見てやる気を失う、多数の社員の士気の低下が大きな損失だ。
すでに警告を発する段階は過ぎているかもしれないが。
企業の金もうけのために、提言をしようというわけではない。
人は働けばよいとも思わない。
ただ、所属する組織が、こんな状態では、人間として不幸だ。
うっぷんまじりと言われても、考えをまとめてみたくなった。
仕事は、確かに労働者が疎外感を抱く、苦痛を伴う負担 burden となりがちだが、
仕事を通した自己実現ということもあり得る。
そうした考え方を持ち、かつ、それができる能力を備えながら、意義の感じにくい、閑職をあてがわれたら、
人のやる気 motivation はなかなか維持できない。
「会社が、そういう使い方をするのなら、あくせくしても始まらない」「のんびりやらせてもらう」
「後は、寄生するだけだ」などとふてくされてしまうのも理解できる。
もちろん、人事はある程度置き換え可能で、
AがBに代わったからといって、それが失敗だったかどうか、はっきり表れることはまれだろう。
やり直すこともできないから、検証も無理だ。
だが、理屈としては、企業衰退の足取りを速める大きな要因となるだろうことが容易に想像できる。
⇒PAGE TOP
| 企業に徳はないが |
| ○年○月○日 |
企業倫理を考えるとき、思い出す古い本がある。
アンドレ・コント=スポンヴィルの『資本主義に徳はあるか』(紀伊國屋書店)。
スポンヴィルが言うように、企業に道徳を求めるのは、お門違いであるかもしれない。
経済は道徳と無縁に動く。企業は道徳的でも反道徳的でもなく、「非道徳的」なものであると言う。
企業の主たる目的は利益の追求であり、従業員を道徳的に雇用したり、商品を道徳的に生産するわけではない。
道徳にかなう商品が開発されることはあろうが、それは、企業の利益とたまたま一致したからだ。
もちろん反道徳を目指すものでもない。そんなことをすれば顧客の支持を失い、存続さえ難しくなるだろう。
企業が顧客を裏切らないのは、信用を失うことが商売の上で不利益になるからだ。
カントが例を挙げているように、商人が道徳にかなった仕方で、義務にかなった仕方で振る舞っていても、
それは道徳的な義務によって振る舞っているのではなく、利害によってのことなのだ。
だから、商道徳と言っても本来の道徳ではない。
行為の道徳的価値の特徴は利害から離れていることだからだ−。
と、ここまではすべて彼の受け売り、というか私の理解したことだ。
彼の整理は確かに面白い。のみならず分かりやすい。だが…。
企業に道徳や人間的な誠実さを求めることは無理にしても、
彼も言う通り、経営者は個人であり、道徳的でも反道徳的でもあり得る。
つまり、経営者や幹部、企業の構成員それぞれは、道徳的であるべきだということは言えるだろう。
しかし彼らは、時として自らに不誠実で、あるいは人間自体が卑劣であるし、反道徳的な意思決定をすることもある。
その際は、企業活動に個人の意思が反映されるから、その企業活動は反道徳的になるだろう。
経済的に不利がないのなら、企業の論理から糾弾されることはない。
一方、道徳的に批判されるべき場合でも、はっきり目に見える形で表沙汰にならないと、
なかなか制裁を受けることにはならないだろう。
ここに欲求不満がある。
欲求不満は、それだけではない。
もし、経営者が経済的に妥当でない意思決定をしたとしても、その適否がストレートに見えることは少ない。
さまざまなファクターに隠れて、何が何だか分からないのが普通だ。
経営者の(のみならず幹部の、ひいては組織の)一々の決定、行為を抽出して分析するなど、効率に反する作業だから、
「非生産的」で「無駄なこと」になってしまう。
「そんなことをやってる暇があったら、一つ余計に売ってこい」と言うわけだ。
こうした構造が、いわゆる「隠れ蓑」になっている。
かくして、人格破綻の経営者も、経営能力に疑問のある経営者も、そのポストに居座り続けることができるのだ。
⇒PAGE TOP
| 在職死亡と特進 |
| ○年○月○日 |
リーマン・ショック直前のことだ。後輩が若くして病死した。
死亡日付で昇格人事が発令され、同時に死亡退職となった。
こうした措置を、それまで、とくにおかしいと意識したことはなかった。 日本企業の「温情」のようなものに自然になじんでいた。
企業業績に貢献してきたであろう死者の労に報い、その遺族を経済的に支援する意味合いから、退職金算定に反映させる。企業はその分、支出を増やす。
ここで、企業論を書こうというのではない。 書き始めたのは、ふと、軍隊を思い浮かべたからだ。
戦争では、「名誉の戦死」をさせられた兵士の階級が上がる。この感覚が、企業の中に脈々と受け継がれてきたのではないかと。
その前年の2月、板橋区の東武線踏切に入った女性を助けようとして殉職した巡査部長は、2階級特進で警部になった。
こちらは、軍隊と同様の階級社会であり、かつ退職金は税金から出るので、発令に懐が痛む感覚はないかもしれない。
コストに敏感な民間企業も同様の伝統を受け継いでいることが興味深いのだ。
貴重な人材を失った上に、将来的にほとんど見返りのないコストをかけ損失を拡大する。
もし貴重でない人材なら、賃金の後払い的な解釈も難しいだろう。
経済合理性を追求すれば、処遇の「特進」は捨てるべき対応ではないのか。
では、なにゆえに続いているのか。日本以外の国では、どうしているのだろう。
考えてみれば、軍隊用語が流通する企業文化は日本の多くの会社で見られる。
「指揮官がしっかりしなければだめじゃないか」「私は一兵卒ですから」「兵站」「絨毯爆撃」「同期の桜」など、意識せずに使っている言葉は多い。
もっとも、企業活動が本来、競争であり、戦いであるならば、こうした用語が便利な表現として使われるのは当然と言えなくもないのだが。
⇒PAGE TOP
| 経営者の不作為 |
| ○年○月○日 |
日本の主要企業の経営者は、創業者や大株主というよりも、社員上がりの生え抜きが多い。
組織内の競争に勝ち残って階段を上ってきた「サラリーマン社長」「サラリーマン役員」である。
感覚的に言えば、経営責任に対する自覚の低さと、こうした事情は無縁でないように思う。
もちろん、それを論証するには緻密な作業がなければならないが。
一般化することも安易にはできないが、定年退職とならず、高額な所得を得られる期間が延長されるという程度の感覚の人も多いのではないか。
激しい実力主義あるいは権力争いで息の抜けない会社は別にしても、60代以上の役員がほとんどという会社は、往々にしてこの傾向が感じられる。
首尾良く経営陣に加わっても、何期何年くらいその座にとどまれるかは、おおよそ見当がつく。
自ら興した会社でもなく、株式も持ち続けられないなら、この先、経営が傾こうと知ったことではない。
何より、この企業が決して胸を張れる体質でないことは、知り尽くしているじゃないか。「さわらぬ神にたたりなし」だ。
不合理や不正義に気づいても、何もしない方がリスクは小さく利益は大きい。
余計なことに手を付けるより、じっと波風立てずに過ごした方がいい。
自分ももう年だ。何をあえて苦労する必要があるのだ。
矛盾も見ないようにしていれば、後で問題になっても自分はもう辞めている。
そうやって「不作為」が積み重ねられる。
その期間が長いほど、不利益をこうむる社員も多いのだが、無責任経営者には実感がない。どうでもいいことなのだ。
ある意味、彼らは割り切っているのかもしれない。
あるいは、そもそも良心の呵責に苦しまないように、無意識のうちにsympathyをまひさせる自己防衛のmechanismが働いているのかもしれない。
悪人とは言えなくても、自覚なく能天気に幸せな老後を過ごすのなら、割を食う側の彼らに対するストレスは募る。
⇒PAGE TOP
| メルケル首相 |
| ○年○月○日 |
世界に拡散され感動を広げているメルケル首相の「魂の演説」。
知るのが遅れてしまったが、見られてよかった。
言葉の壁を越えて、気持ちがびんびん伝わってくる。胸がいっぱいになる。
Merkel tief besorgt-eindringlicher Appell imBundestag(DW News)
09.12.2020@dwnews
https://twitter.com/i/status/1336616315021389824 (DW News)
@dwnews・ 12月9日
"I really am sorry, from the bottom of my heart.But if the price we pay is 590 deaths a day, then that is unacceptable in my view."
German Chancellor Angela Merkel begsGermans to follow coronavirus restrictions in anunusually emotional appeal ahead of Christmas.
https://twitter.com/i/status/1336607689204518914 (ARD)
日本は、よりによって日本人の中でも最低レベルの人間が2代続けて首相になっている。
⇒PAGE TOP
| 過剰敬語 |
| ○年○月○日 |
喪中のはがきに「どうぞ良い年をお迎えになられますようお祈り申し上げます」と書いた。
いわゆる「二重敬語」である。言葉にうるさい人からは「日本語を知らないやつだ」とばかにされるだろう。
確かに私も、以前なら同じ反応をしていたように思う。言葉遣いとして誤りであることは認めざるを得ない。
「〜になる」で、相手に対する敬意は十分払われている。ここは「どうぞ良い年をお迎えになりますよう」で不足はないはずだ。
しかし、書いてみると何か落ち着かない。読み直すと「お祈り申し上げます」とのつながりが悪いのか、どこか丁寧さが足りないような気がしてきた。
この手の挨拶状では、日ごろ使わない、かしこまった文面になるため、丁寧さのハードルが一段上がってしまうのだろうか。
「お迎えになられますよう」と書いてから、さすがに「くどいな」と思わないわけでもなかった。はがきを受け取った人の中にも違和感を持つ人がいるかもしれないから、多少のためらいもあった。しかし「お迎えになりますよう」にはしなかった。同様に敬語1回の「迎えられますよう」も、もっと丁寧さが減じるような気がして採用しなかった。
私の感じ方が特殊なのだろうか。ネットで検索しても、私の感覚を補強してくれる記事はほとんど見当たらなかった。わずかに、喜寿メッセージの文例として「つつがなく喜寿をお迎えになられた由...」というのを見つけた。恐らくは冠婚葬祭の業界の人が書いたのだろう。あらたまった行事などでは、必要以上に丁重な方向に形式が変わりがちなのかもしれない。
時折、「日本語を知らないやつだ」と指摘があるのは、こうした「誤用」をする人がある程度存在するからだ。とくに日常、なじみの薄い表現については、言い慣れてないので(聞きなれてないので)ネイティブとしての語感もあやふやだ。それぞれの直感で言葉を選んでいる。普通、文法は考えていない。日常語としての「お越しになられる」「お見えになられる」には、地域や世代によって違和感のない人も多いのではないか。
重言(重複表現)も一般に冗長で過剰となることは事実だが、かつてのように全否定されなくなってきた。言葉を重ねることが強調の用法としてオーソライズされていることもある。考えてみれば「御御御付」「豌豆豆」を誤用と言う人はいないだろうし、「一番最後」に目くじらを立てる人も少ないだろう。そう考えると、敬語の規範も不変であるはずがない。
⇒PAGE TOP
先頭のページ 前のページ 次のページ 末尾のページ